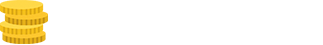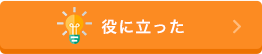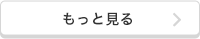■寡婦控除で税金が安くなる
夫が亡くなった後の妻に対する税金の制度として「寡婦控除」があります。
個人の所得に対して所得税や住民税が課税されるのですが、この税額計算の時に、寡婦(*1)の場合は、控除を増やし納める税金が安くなるというものです。
*1夫と死別または離婚をし、その後婚姻をしていない人
・扶養親族がいる又は生計を一にする子(総所得金額等が38万円以下、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合)は所得制限なし
・扶養親族などがいない場合は所得制限あり(合計所得金額が500万円以下)
遺族年金の収入には所得税や住民税はかからず非課税となりますが、アルバイトや会社員などの給料には所得税や住民税がかかります。この税額は、収入から様々な控除をひいた所得より決まります。
この控除の中のひとつが「寡婦控除」です。
一般的に、年収103万円までであれば所得税がかからないといわれます。それは、給与所得控除(給与所得者の経費と換算されるもの。最低65万円)と、だれでも受けられる基礎控除38万円を合計した103万円。
つまり、年収103万円までのアルバイト収入であれば所得がゼロとなり所得税はかかりません。いわゆる非課税枠ですね。
寡婦控除額は27万円(特定の寡婦(*2)は35万円)なので、寡婦の方の非課税枠は、103万円に27万円(特定:35万円)を加算した、130万円(特定:138万円)となります。
*2 扶養親族である子がおり合計所得が500万円以下である寡婦
また、相談者のように扶養親族に所得税法上の障害者がいる場合は、障害者控除も加わります。
障害者控除額は、障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円(*3)。
*3 特別な障害:特別障害者、更に同居:特別同居障害者
寡婦控除に障害者控除(27万円or40万円or75万円)が加わると、非課税枠は157万円から213万円の範囲となります。
その他にも、支払った国民健康保険料は、その全額が社会保険料控除として適用され、非課税枠は増えます。
国民健康保険料は自治体によって計算方法が変わります。実際には、年間所得や保有資産などに応じて保険料が決まります。
所得が増える場合、多くの自治体では増えた所得に対して年間5%~15%程度の保険料増額となるようです。
次に、年金について。
亡くなった夫が会社員(第2号被保険者)であった場合、残された妻は遺族厚生年金が受給できます。また、一定条件(*4)を満たせば、妻が65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。
*4夫の死亡時、夫により生計維持されており、妻が40歳以上、または40歳時に遺族基礎年金を受給している子がいる
相談者の方は、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算を受給していると思われます。
中高齢寡婦加算は妻自身が65歳になれば支給停止となり、代わって妻自身の老齢基礎年金が受給できます。
中高齢寡婦加算額は、老齢基礎年金の満額の4分の3。
満額とは、国民年金に全期間40年保険料を納めた場合(会社員の被扶養配偶者である第3号被保険者期間含む)で、実際の年金額は保険料納付期間に比例します。
65歳で中高齢寡婦加算から老齢基礎年金変更になる時、国民年金保険料納付期間が4分の3、つまり30年以上であれば年金額は増えますが、30年に満たない場合は減ることになります。
いずれも、年金を受け取れる年齢になると、年金請求書が送られてきます。
遺族厚生年金を継続受給したい場合は、その旨を申請する必要があります。
年金事務所か年金相談センターで手続きをするといいでしょう。
また、厚生年金の加入対象年齢は70歳までですので、厚生年金に加入する働き方(勤務日数など)であれば60歳を過ぎても厚生年金に加入することになります。
国民年金は60歳を過ぎると加入する必要はありません。